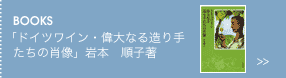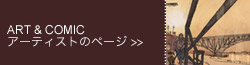TRANS・BRASIL ブラジル・日本往復

松山にある伊丹十三記念館




カフェ「タンポポ」のメニューには伊丹さんが好きだったと言うシャンパンのオレンジジュース割り「ミモザ」もあった。
020「伊丹十三記念館へ」
2015年の晩秋に、神戸から日帰りで松山へ行った。列車で瀬戸大橋を渡り、四国を西進する。見知らぬ瀬戸内の海はとても広い。降り立った松山には、まだ昭和の香りが残っていた。
行き先は「伊丹十三記念館」。黒い板塀のシンプルな造り。修道院建築のように、中庭とそれを囲む回廊がある。私の一番好きな建築構造だ。中庭には寄り添うように生える2本の桂の木。よく見るとそれは1本の木で、2本に株がわかれている。伊丹さんと奥様の宮本信子さんが寄り添って立っている姿の木なのだと教えてもらった。
伊丹さんの本名は池内義弘さん。1933年生まれ。中一のとき、お父さんを亡くされた。お父さんは映画監督や脚本家,俳優として活躍した伊丹万作氏で、彼の故郷が松山なのだという。伊丹さんは親子ともにマルチタレントで、ひとつの職業に縛られなかった。
いろいろなジャンルにおいて先進的な人だったようだが、エッセイの分野において、人に話しかけるような文体を書いたのは、彼が初めてだったと言う。60年代から70年代にかけてのことだ。「〜であるわけね」「〜なのだな」「〜そういうものかね」といった、柔らかな文末を目にすると、伊丹さんがそこにおられるような気がしてくる。
記念館の展示は変化に富み、全く飽きさせない。気がついたら閉館時間だった。
伊丹さんは、食に拘りがあり、本格的なスパゲティの茹で方(アルデンテ)や野趣あふれるサラダなどを提案した。「一番大切なのは舌、味覚である」。そしてその味覚はかならずしも美食ということではなく、味の深みを知っているか否かである、という伊丹さんの味覚論。その伊丹さん秘伝の厚焼き玉子のレシピには「味の素少々」とある。味の素が食卓に欠かせない調味料だった時代を思い出した。
私が伊丹さんを初めて知ったのは、80年代のことだ。大学時代、彼が創刊した「モノンクル(ぼくのおじさん)」という不思議な雑誌をなぜか毎号買っていた。あの雑誌を、今もう一度読んでみたいと思う。あの頃の私は、なぜあの雑誌に魅かれたのだろう?
その後の伊丹さんは、映画監督であり続けた。移住したドイツでは、80年代後半から90年代にかけて、伊丹さんの「タンポポ」(1985)が頻繁に上映され、ドイツ人の友人たちと何度も観に出かけた。
伊丹さんは、映画にできそうな食に関するディティール、食にまつわるエピソードをいろいろ集めておられたそうだが、その「容れ物」なかなかみつからなかった。ところがある日、西部劇を思いつき、2日で脚本ができたという。「タンポポ」の誕生だ。伊丹さん自身はラーメン通でもなく、ラーメン屋にはほとんどいかなかったそうで、でき上がった脚本は伊丹さん自身にとっても驚きだったという。
伊丹さんの映画は「お葬式」で始まる。
1984 お葬式
1985 タンポポ
1987 マルサの女
1988 マルサの女2
1989 スウイートホーム
1990 あげまん
1992 ミンボーの女
1993 大病人
1995 静かな生活
1996 スーパーの女
1997 マルタイの女
精力的に映画を作られた晩年だった。
伊丹さんの命日は1997年12月20日。64年の人生。もっと長く生きて、もっと色々な作品を見せていただきたかった。私の父は伊丹さんより3つ年上で、伊丹さんが亡くなる1年前にこの世を去った。65年の人生。心から語り合いたいと思った時、父はもうこの世にいなかった。父の世代のエッセンスは、その後に読んだ伊丹さんの本から教えてもらった。その意味で、伊丹さんは私のモノンクルだ。
伊丹さんが語ったとても好きな言葉がある。
「麦と稲の区別さえ満足にできぬ我々都会人が、どうして農家のおかみさんと世間話ができましょうか?」
ワイナリーを取材するとき、いつも伊丹さんのこの言葉を思い出す。
ARCHIV
過去のブラジルと日本をめぐるエッセイはトップページのアーカイヴからお探しください。
2015年の晩秋に、神戸から日帰りで松山へ行った。列車で瀬戸大橋を渡り、四国を西進する。見知らぬ瀬戸内の海はとても広い。降り立った松山には、まだ昭和の香りが残っていた。
行き先は「伊丹十三記念館」。黒い板塀のシンプルな造り。修道院建築のように、中庭とそれを囲む回廊がある。私の一番好きな建築構造だ。中庭には寄り添うように生える2本の桂の木。よく見るとそれは1本の木で、2本に株がわかれている。伊丹さんと奥様の宮本信子さんが寄り添って立っている姿の木なのだと教えてもらった。
伊丹さんの本名は池内義弘さん。1933年生まれ。中一のとき、お父さんを亡くされた。お父さんは映画監督や脚本家,俳優として活躍した伊丹万作氏で、彼の故郷が松山なのだという。伊丹さんは親子ともにマルチタレントで、ひとつの職業に縛られなかった。
いろいろなジャンルにおいて先進的な人だったようだが、エッセイの分野において、人に話しかけるような文体を書いたのは、彼が初めてだったと言う。60年代から70年代にかけてのことだ。「〜であるわけね」「〜なのだな」「〜そういうものかね」といった、柔らかな文末を目にすると、伊丹さんがそこにおられるような気がしてくる。
記念館の展示は変化に富み、全く飽きさせない。気がついたら閉館時間だった。
伊丹さんは、食に拘りがあり、本格的なスパゲティの茹で方(アルデンテ)や野趣あふれるサラダなどを提案した。「一番大切なのは舌、味覚である」。そしてその味覚はかならずしも美食ということではなく、味の深みを知っているか否かである、という伊丹さんの味覚論。その伊丹さん秘伝の厚焼き玉子のレシピには「味の素少々」とある。味の素が食卓に欠かせない調味料だった時代を思い出した。
私が伊丹さんを初めて知ったのは、80年代のことだ。大学時代、彼が創刊した「モノンクル(ぼくのおじさん)」という不思議な雑誌をなぜか毎号買っていた。あの雑誌を、今もう一度読んでみたいと思う。あの頃の私は、なぜあの雑誌に魅かれたのだろう?
その後の伊丹さんは、映画監督であり続けた。移住したドイツでは、80年代後半から90年代にかけて、伊丹さんの「タンポポ」(1985)が頻繁に上映され、ドイツ人の友人たちと何度も観に出かけた。
伊丹さんは、映画にできそうな食に関するディティール、食にまつわるエピソードをいろいろ集めておられたそうだが、その「容れ物」なかなかみつからなかった。ところがある日、西部劇を思いつき、2日で脚本ができたという。「タンポポ」の誕生だ。伊丹さん自身はラーメン通でもなく、ラーメン屋にはほとんどいかなかったそうで、でき上がった脚本は伊丹さん自身にとっても驚きだったという。
伊丹さんの映画は「お葬式」で始まる。
1984 お葬式
1985 タンポポ
1987 マルサの女
1988 マルサの女2
1989 スウイートホーム
1990 あげまん
1992 ミンボーの女
1993 大病人
1995 静かな生活
1996 スーパーの女
1997 マルタイの女
精力的に映画を作られた晩年だった。
伊丹さんの命日は1997年12月20日。64年の人生。もっと長く生きて、もっと色々な作品を見せていただきたかった。私の父は伊丹さんより3つ年上で、伊丹さんが亡くなる1年前にこの世を去った。65年の人生。心から語り合いたいと思った時、父はもうこの世にいなかった。父の世代のエッセンスは、その後に読んだ伊丹さんの本から教えてもらった。その意味で、伊丹さんは私のモノンクルだ。
伊丹さんが語ったとても好きな言葉がある。
「麦と稲の区別さえ満足にできぬ我々都会人が、どうして農家のおかみさんと世間話ができましょうか?」
ワイナリーを取材するとき、いつも伊丹さんのこの言葉を思い出す。
過去のブラジルと日本をめぐるエッセイはトップページのアーカイヴからお探しください。