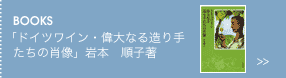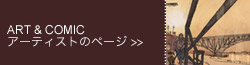BACK TO HAMBURG 追憶のハンブルク・未知のドイツ

フリードリヒシュトラーセ駅のホームには、まだほんの少し旧東独時代の陰りが感じられる

駅舎を出ると、そこは東ベルリンだった

修復された「涙の宮殿」は現在博物館となっている。入場無料

1980年の夏も「涙の宮殿」からこんな風景が見えたのだろうか

80年代、この細長い検問所を通って西側に戻った

東ドイツのビザ。これは1988年に旅した時のもの
027 「ベルリン 1980年の夏」
私のベルリン、それはかつての西ベルリンだ。今でもベルリンへ行くと、一度はツォー駅で下車し、クーダム(クアフュルステンダム大通り)を歩かないとなんだか落ち着かない。そうしないと、ベルリンに来た気がしない。
まだベルリンの壁が立ちはだかっていた80年代半ば、リオ生まれのドイツ人の友人がシャルロッテンブルク地区に住んでいた。彼を訪ねて、ハンブルクとベルリンを何度も往復した。「相乗りセンター(Mitfahrerzentrale)」というサービスを利用して、ベルリンに行く営業マンなどの車に片道5マルクくらい払って乗せてもらった。
西ベルリンまでの道は、監視されている休憩場を除いて下車したり、道を外れたりできない。トランジット区間の東ドイツの田舎の風景は、現実感のないモノクロームの映像として頭の片隅にある。西ベルリンに近づくと、街に色彩と音がつきはじめた。
記憶の地図には、ハンブルクのすぐ隣に西ベルリンがあり、その間はすっぽりと抜けている。当時よく歩いたシャルロッテンブルク地区を歩くと、いまだに東の方角には、まだ東西を分断する壁があり、その向こうに灰色の東ベルリンが存在するような気さえする。
***
初めてベルリンへ行ったのは、1980年の夏だった。当時リューネブルクにゲーテ・インスティトゥートがあり、大学の夏休みを利用して夏期コースに参加した時のことだ。ある週末、クラスでベルリンへ行った。バスで行ったのか、列車だったか、記憶が定かでない。
確か、クーダムの脇道の天井の高い安宿に宿泊した。ベルリンの建物はそれまで知っていた街よりひと回り大きかった。翌日、フリードリヒシュトラーセ駅に向かった。日帰りで東ベルリンを訪れるためだ。
当時、フリードリヒシュトラーセ駅は国境駅になっていて、ここで東西ベルリンへの出入国審査が行われた。長い通路を歩き、階段を登り下りして駅舎に移動すると、パスポートコントロールがあり、その場で1日だけ有効なビザがもらえた。この時、簡単な荷物検査があり、持っていた西側のニュース雑誌を没収されたことと、没収した係員の嬉しそうな顔を今でも思い出す。雑誌は仲間で回し読みしたことだだろう。コントロールキャビンを通過すると、今度は強制両替。規定額の25マルクを1対1でオストマルクに替えてもらって駅舎を出た。
出てすぐに目指したのはブランデンブルク門。西からは壁が邪魔して、決して近づけなかった建築物が目の前に聳える。ウンター・デン・リンデン、共和国宮殿(Palast der Republik)、ペルガモン博物館、アレキサンダー広場とお決まりのコースを回った後、手元にまだオストマルクがたっぷり余っていることに気がついた。再両替できないので、使い切るしかない。
フリードリヒシュトラーセ駅の近くに、当時最新の高層ビルがあり、そこにレストランがあるという情報を得て、私たちは、残りのお金を使い切るためにそこに向かった。現在、ここは国際貿易センターになっている。調べてみるとビルは1978年に竣工、鹿島建設の設計・施工だと知って驚いた。何を食べたかはもう忘れてしまったが、当時の東ドイツのどのレストランにもあったソルヤンカと呼ばれる野菜スープと、一番高かった肉料理を食べたのではないかと思う。それでもオストマルクは余った。
帰りは「涙の宮殿(Tränenpalast)」と呼ばれる建物で出国審査を受け、入り組んだ通路を経て駅に戻った。ベルリンの壁が築かれたのは1961年。涙の宮殿も同じ年に建てられ、1989年まで西行きの検問所として機能した。壁のあった時代、東独市民に対し、西側への旅行はごく限られた場合にだけ認められた。一方で西側からは家族や友人が訪ねて来る。この建物は東への訪問者たちと東独市民のお別れの場所だった。それで、涙の宮殿と呼ばれた。
半日を東ベルリンで過ごし、戻って来た西ベルリンは、より一層きらびやかだった。その夜、クラスメートとクーダムの映画館に行った。たしかフィルムパラスト(Filmpalast)という名前の映画館だった。何を観たのかは忘れてしまったが、 座席に着いてふと前方を見ると、色白の小柄で華奢な女性がいた。小さな帽子、ぴったりとオイルで撫で付けたウエーブのかかったショートカット、くっきりとしたアイメイク、深紅の口紅。白っぽい細身のワンピースはローウエストの切り替え。写真でしか知らなかった20〜30年代風のファッション。まるでヴァイマル時代の女優のような彼女に、私は釘付けになってしまった。彼女が目の前に現れたことで、1980年の真夏のベルリンが、一瞬にしてヴァイマル共和国時代のベルリンになった。
あれからもう37年たつが、ベルリンのことを想うとき、彼女の姿を鮮明に思い浮かべることができる。彼女を見てしまったせいだろうか、その後私は1985年から1988年にかけて、ヴァイマル文化の痕跡を探し求めてベルリンと旧東独の地方都市をあちこち訪れた。
***
1989年10月、ベルリンの壁が崩壊したその日、私は東京にいた。1年契約で東京の出版社に勤めることになり、東京暮らしを始めたばかりだった。ベルリン発のニュースはにわかに理解し難く、遠い国の夢のような出来事に思えた。1年後、ハンブルクに再び戻った時に、見慣れないトラバントが沢山駐車している道路や、かつてない住宅難に遭遇し、やっと状況を肌で理解した。
壁が崩壊してからも何度もベルリンに行っている。行くたびにベルリンが持っていた闇の部分はどんどん消え、街は西側の色に染まっていった。昨年ベルリンに行った時、あのヴァイマル時代の女優のような彼女に出会った映画館が残っているかどうか探してみた。カフェ・クランツラーの向い側に見つかったのは、アストア(Astor)という映画館だった。1948年からある映画館だと言うから、きっとここがフィルムパラストだったのだろうと思う。残念ながらハンブルクに戻る時間が迫っていて、映画館の中には入れなかったが、記憶にはなかったロビーで、1980年の夏の日のことを思い出していた。
ARCHIV
過去のハンブルクエッセイはトップページのアーカイヴからお探しください。
私のベルリン、それはかつての西ベルリンだ。今でもベルリンへ行くと、一度はツォー駅で下車し、クーダム(クアフュルステンダム大通り)を歩かないとなんだか落ち着かない。そうしないと、ベルリンに来た気がしない。
まだベルリンの壁が立ちはだかっていた80年代半ば、リオ生まれのドイツ人の友人がシャルロッテンブルク地区に住んでいた。彼を訪ねて、ハンブルクとベルリンを何度も往復した。「相乗りセンター(Mitfahrerzentrale)」というサービスを利用して、ベルリンに行く営業マンなどの車に片道5マルクくらい払って乗せてもらった。
西ベルリンまでの道は、監視されている休憩場を除いて下車したり、道を外れたりできない。トランジット区間の東ドイツの田舎の風景は、現実感のないモノクロームの映像として頭の片隅にある。西ベルリンに近づくと、街に色彩と音がつきはじめた。
記憶の地図には、ハンブルクのすぐ隣に西ベルリンがあり、その間はすっぽりと抜けている。当時よく歩いたシャルロッテンブルク地区を歩くと、いまだに東の方角には、まだ東西を分断する壁があり、その向こうに灰色の東ベルリンが存在するような気さえする。
***
初めてベルリンへ行ったのは、1980年の夏だった。当時リューネブルクにゲーテ・インスティトゥートがあり、大学の夏休みを利用して夏期コースに参加した時のことだ。ある週末、クラスでベルリンへ行った。バスで行ったのか、列車だったか、記憶が定かでない。
確か、クーダムの脇道の天井の高い安宿に宿泊した。ベルリンの建物はそれまで知っていた街よりひと回り大きかった。翌日、フリードリヒシュトラーセ駅に向かった。日帰りで東ベルリンを訪れるためだ。
当時、フリードリヒシュトラーセ駅は国境駅になっていて、ここで東西ベルリンへの出入国審査が行われた。長い通路を歩き、階段を登り下りして駅舎に移動すると、パスポートコントロールがあり、その場で1日だけ有効なビザがもらえた。この時、簡単な荷物検査があり、持っていた西側のニュース雑誌を没収されたことと、没収した係員の嬉しそうな顔を今でも思い出す。雑誌は仲間で回し読みしたことだだろう。コントロールキャビンを通過すると、今度は強制両替。規定額の25マルクを1対1でオストマルクに替えてもらって駅舎を出た。
出てすぐに目指したのはブランデンブルク門。西からは壁が邪魔して、決して近づけなかった建築物が目の前に聳える。ウンター・デン・リンデン、共和国宮殿(Palast der Republik)、ペルガモン博物館、アレキサンダー広場とお決まりのコースを回った後、手元にまだオストマルクがたっぷり余っていることに気がついた。再両替できないので、使い切るしかない。
フリードリヒシュトラーセ駅の近くに、当時最新の高層ビルがあり、そこにレストランがあるという情報を得て、私たちは、残りのお金を使い切るためにそこに向かった。現在、ここは国際貿易センターになっている。調べてみるとビルは1978年に竣工、鹿島建設の設計・施工だと知って驚いた。何を食べたかはもう忘れてしまったが、当時の東ドイツのどのレストランにもあったソルヤンカと呼ばれる野菜スープと、一番高かった肉料理を食べたのではないかと思う。それでもオストマルクは余った。
帰りは「涙の宮殿(Tränenpalast)」と呼ばれる建物で出国審査を受け、入り組んだ通路を経て駅に戻った。ベルリンの壁が築かれたのは1961年。涙の宮殿も同じ年に建てられ、1989年まで西行きの検問所として機能した。壁のあった時代、東独市民に対し、西側への旅行はごく限られた場合にだけ認められた。一方で西側からは家族や友人が訪ねて来る。この建物は東への訪問者たちと東独市民のお別れの場所だった。それで、涙の宮殿と呼ばれた。
半日を東ベルリンで過ごし、戻って来た西ベルリンは、より一層きらびやかだった。その夜、クラスメートとクーダムの映画館に行った。たしかフィルムパラスト(Filmpalast)という名前の映画館だった。何を観たのかは忘れてしまったが、 座席に着いてふと前方を見ると、色白の小柄で華奢な女性がいた。小さな帽子、ぴったりとオイルで撫で付けたウエーブのかかったショートカット、くっきりとしたアイメイク、深紅の口紅。白っぽい細身のワンピースはローウエストの切り替え。写真でしか知らなかった20〜30年代風のファッション。まるでヴァイマル時代の女優のような彼女に、私は釘付けになってしまった。彼女が目の前に現れたことで、1980年の真夏のベルリンが、一瞬にしてヴァイマル共和国時代のベルリンになった。
あれからもう37年たつが、ベルリンのことを想うとき、彼女の姿を鮮明に思い浮かべることができる。彼女を見てしまったせいだろうか、その後私は1985年から1988年にかけて、ヴァイマル文化の痕跡を探し求めてベルリンと旧東独の地方都市をあちこち訪れた。
***
1989年10月、ベルリンの壁が崩壊したその日、私は東京にいた。1年契約で東京の出版社に勤めることになり、東京暮らしを始めたばかりだった。ベルリン発のニュースはにわかに理解し難く、遠い国の夢のような出来事に思えた。1年後、ハンブルクに再び戻った時に、見慣れないトラバントが沢山駐車している道路や、かつてない住宅難に遭遇し、やっと状況を肌で理解した。
壁が崩壊してからも何度もベルリンに行っている。行くたびにベルリンが持っていた闇の部分はどんどん消え、街は西側の色に染まっていった。昨年ベルリンに行った時、あのヴァイマル時代の女優のような彼女に出会った映画館が残っているかどうか探してみた。カフェ・クランツラーの向い側に見つかったのは、アストア(Astor)という映画館だった。1948年からある映画館だと言うから、きっとここがフィルムパラストだったのだろうと思う。残念ながらハンブルクに戻る時間が迫っていて、映画館の中には入れなかったが、記憶にはなかったロビーで、1980年の夏の日のことを思い出していた。
過去のハンブルクエッセイはトップページのアーカイヴからお探しください。