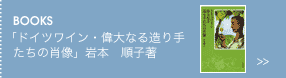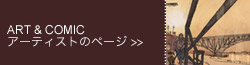BACK TO HAMBURG 追憶のハンブルク・未知のドイツ

アンドレアスが描いたオーバーハーフェン・カンティーネ ©Andreas Dierssen

新装オープンしたオーバーハーフェン・カンティーネ

ここにいるとアニタさんを思い出す

新しい鉄橋。食堂は今も傾いたまま立っている
004「ある食堂のちいさな歴史 オーバーハーフェン」
ハンブルク、オーバーハーフェン地区。ちょっと寂れた感じの港の一角に、たぶんハンブルクで一番小さな食堂がある。オーバーハーフェン・カンティーネ(Oberhafen Kantine)だ。
ピサの斜塔のように傾いた、この食堂のことを知ったのは、1991年のこと。リューネブルク近郊に住むコミック作家、アンドレアス・ディアセン(Andreas Dierssen)の「愛と死とその他の残酷な物語」という作品中でだった。描かれていた食堂があまりにも魅力的だったので、そうアンドレアスに言ったら、実在する食堂だと教えてくれた。
以来私は、数えきれないほど、この食堂に通った。日本から母や親戚、友人が来るたび、ここに案内した。当時は、アニタ・ヘンデル(Anita Haendel)さんというおばあちゃんが店を切り盛りしており、他に年配の男性と、もうひとりおばあちゃんのスタッフがいた。注文したスープがテーブルに置かれると、傾いていまにもこぼれそうになった。
当時の食堂の常連は港湾労働者たちだった。彼らは自宅の台所にでもいるかのように、カウンターからビールやオープンサンドを自由にとりだして飲み食いしていた。きっと忙しいアニタさんの手間を省いてあげていたのだろう。メニューらしきものはなく、だいたいいつも、スープと肉料理があった。丁寧につくられた優しい味のシュニッツェルには、グリーンピースと人参をバターでさっと炒めただけのシンプルな副菜が添えられた。どれも、あの頃のごく普通のドイツの家庭料理だった。
この食堂へ出かける時は、いつもワクワクした。ダイヒトアハレ(美術展会場)を通り過ぎたところにある鉄橋を渡ってゆくのだが、その古めかしい橋がとても素敵だった。そこだけが、空想の中で、パリになったり、ニューヨークになったりした。改修された現在の鉄橋は、なんだかすっきりしすぎて、味気ないのが残念だ。
この建物は、食堂主のヘルマン・シュパー(Hermann Sparr)氏の依頼で、1925年に完成した。設計はヴィリー・ヴェーグナー(Willy Wegner)氏で、煉瓦造りの表現主義様式。この年には、同じ様式の特筆すべき建築「チリハウス(Chilehaus)」(建築主はチリとの取引で財を成した船主)も建てられており、ともに同じ煉瓦が使われているそうだ。私が1990年代にお会いしたアニタさんは、ヘルマン・シュパー氏の娘で、12歳の時から亡くなる直前まで、72年間この食堂で働いていたという。
1997年の春にアニタさんが亡くなられたというニュースは新聞で読んだ。その後まもなく、ハンブルク市は、倒壊の恐れがあるという理由で、この建物を閉鎖してしまった。一時は、取り壊しの噂も流れた。しかし2000年には保護文化財に指定され、2002年にはハンブルクの投資家がこの物件を購入、2005年から大掛かりな改修工事が始まった。
9年間のブランクを経て、食堂が再出発したのは2006年の春。若手の料理人としてマスメディアで活躍中のティム・メルツァー(Tim Mälzer)のお母さん、クリスタさんが店を継いだ。ところが、2007年の秋に地下の台所が浸水し、クリスタさんは経営を断念する。そして2008年春、今度はトルステン・ジレール氏(Thorsten Gillert)が店を継いだ。彼は亡きアニタさんのアシスタントを勤めたこともあるそうで、料理もアニタさんの時代を思い起こさせるものだ。
オーバーハーフェン・カンティーネは、客層が変わったことを除けば、20年前とあまり変わらない。ここにいると、向こう岸のハンブルクがまだ20年前のままであるかのような錯覚におちいる。カウンターに目をやると、アニタさんの姿が見える。川を渡ることで起こるマジックかもしれない。
ARCHIV
ハンブルク、オーバーハーフェン地区。ちょっと寂れた感じの港の一角に、たぶんハンブルクで一番小さな食堂がある。オーバーハーフェン・カンティーネ(Oberhafen Kantine)だ。
ピサの斜塔のように傾いた、この食堂のことを知ったのは、1991年のこと。リューネブルク近郊に住むコミック作家、アンドレアス・ディアセン(Andreas Dierssen)の「愛と死とその他の残酷な物語」という作品中でだった。描かれていた食堂があまりにも魅力的だったので、そうアンドレアスに言ったら、実在する食堂だと教えてくれた。
以来私は、数えきれないほど、この食堂に通った。日本から母や親戚、友人が来るたび、ここに案内した。当時は、アニタ・ヘンデル(Anita Haendel)さんというおばあちゃんが店を切り盛りしており、他に年配の男性と、もうひとりおばあちゃんのスタッフがいた。注文したスープがテーブルに置かれると、傾いていまにもこぼれそうになった。
当時の食堂の常連は港湾労働者たちだった。彼らは自宅の台所にでもいるかのように、カウンターからビールやオープンサンドを自由にとりだして飲み食いしていた。きっと忙しいアニタさんの手間を省いてあげていたのだろう。メニューらしきものはなく、だいたいいつも、スープと肉料理があった。丁寧につくられた優しい味のシュニッツェルには、グリーンピースと人参をバターでさっと炒めただけのシンプルな副菜が添えられた。どれも、あの頃のごく普通のドイツの家庭料理だった。
この食堂へ出かける時は、いつもワクワクした。ダイヒトアハレ(美術展会場)を通り過ぎたところにある鉄橋を渡ってゆくのだが、その古めかしい橋がとても素敵だった。そこだけが、空想の中で、パリになったり、ニューヨークになったりした。改修された現在の鉄橋は、なんだかすっきりしすぎて、味気ないのが残念だ。
この建物は、食堂主のヘルマン・シュパー(Hermann Sparr)氏の依頼で、1925年に完成した。設計はヴィリー・ヴェーグナー(Willy Wegner)氏で、煉瓦造りの表現主義様式。この年には、同じ様式の特筆すべき建築「チリハウス(Chilehaus)」(建築主はチリとの取引で財を成した船主)も建てられており、ともに同じ煉瓦が使われているそうだ。私が1990年代にお会いしたアニタさんは、ヘルマン・シュパー氏の娘で、12歳の時から亡くなる直前まで、72年間この食堂で働いていたという。
1997年の春にアニタさんが亡くなられたというニュースは新聞で読んだ。その後まもなく、ハンブルク市は、倒壊の恐れがあるという理由で、この建物を閉鎖してしまった。一時は、取り壊しの噂も流れた。しかし2000年には保護文化財に指定され、2002年にはハンブルクの投資家がこの物件を購入、2005年から大掛かりな改修工事が始まった。
9年間のブランクを経て、食堂が再出発したのは2006年の春。若手の料理人としてマスメディアで活躍中のティム・メルツァー(Tim Mälzer)のお母さん、クリスタさんが店を継いだ。ところが、2007年の秋に地下の台所が浸水し、クリスタさんは経営を断念する。そして2008年春、今度はトルステン・ジレール氏(Thorsten Gillert)が店を継いだ。彼は亡きアニタさんのアシスタントを勤めたこともあるそうで、料理もアニタさんの時代を思い起こさせるものだ。
オーバーハーフェン・カンティーネは、客層が変わったことを除けば、20年前とあまり変わらない。ここにいると、向こう岸のハンブルクがまだ20年前のままであるかのような錯覚におちいる。カウンターに目をやると、アニタさんの姿が見える。川を渡ることで起こるマジックかもしれない。