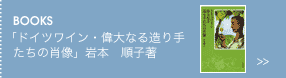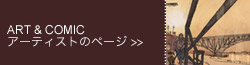TRANS・BRASIL ブラジル往復

チエテ川。編集部からバスでパウリスタ大通り方面へ向かうとき、いつもこの橋を渡った

ブッタンタ地区の高台にある編集部

雑誌用のテイスティングはジャルジン地区のレストランを借り切って
003「サンパウロ初心者マーク」
コマンダント・サンパイオ駅の近くに住んでいた頃、ワイン専門誌、ヴィーニョマガジン編集部でしばらく研修させてもらった。主に、編集のパウラと一緒に雑誌用のテイスティングの準備を担当した。サンパウロで働く人の目線でサンパウロを知ることができた、とても素敵な期間だった。
サンパウロ初心者にとって、一番の難関が通勤だった。サンパウロを走るバスには時刻表がない。また、バス停がわかりにくく、中には、ペイントした木材がぽつんと1本立っているだけの見落としてしまいそうな停留所もある。おまけに走行ルートがさっぱりわからない。当時は、私のポルトガル語など役立たず。掲示されている目的地とボディに取り付けられたいくつかの停留所名のリストを頼りに、思い切って乗ってしまうしかなかった。
毎朝、コマンダント・サンパイオ駅の向かいの大通りのカフェの前で、いつ来るとも知れぬ、ピニェイロス方面行きのバスを待った。ある日の待ち時間は5分ほど。ある日は30分待っても目当てのバスが来ないこともあった。バスはだいたいいつも混んでいた。運転席の方から乗って、中ほどに座っている車掌に料金を払い、回転ドアを解除してもらって奥へ。
よく揺れるのはバスがおんぼろなのか、運転が荒っぽいのか、道路が悪いのか、あるいはサンパウロの起伏のせいなのか。とにかく、どこかにしっかりしがみついていないと、カーブで飛ばされそうになる。カムフラージュのために買物用のずた袋に新聞と一緒につっこんだノートパソコンを片腕でしっかり抱いて、手すりにしがみつくこと約30分。バスを降りるといつもクタクタ。運良く座れたとしても、揺れがひどくて新聞も本も絶対に読めない。
着いたバス停から編集部までの急坂が、これまた休み休みでないと登れなかった。バスから降りると、まず停留所の近くのカフェで一休みしてから坂をのぼったことも何度か。編集部には、すっかり体力を使い果たして到着。
当然のことながら、編集長をはじめ、スタッフのほぼ全員が車で通勤していた。職場が地下鉄駅の近くにないのは致命的だ。雑誌の編集部は出勤時間にさほど制約がないからいいが、勤務時間の決まった会社に勤めている人たちは、いったいどうやって出勤しているのだろう。
ある日、私がバスと徒歩で通っていることを知った編集長が、放っておけないと言って、車で迎えにきてくれることになった。彼は、私がてっきり誰かに車で送り迎えしてもらっているものだと思っていたのだ。見習いが編集長に迎えに来てもらって悠々と出勤するなんて、なんだか立場が逆である。だから、編集長が不在で、自力通勤する日は、逆になんだかほっとした。
帰宅は、行きと違ってちょっと楽だった。急な坂を下り、いつ来るとも知れぬバスを、焦らず待つだけ。でも、仕事の帰りに中心街に寄ってから帰宅する日は勝手が違った。編集部の近くには、棒が1本あるだけのバス停があり、そこに、ジャルジン地区へ向かうバスが時々やってきた。ジェットコースターさながら急坂を猛スピードで下り、チエテ川の橋を越えると今度は渋滞がはじまる。この辺かなと思ったら、天井に張ってある洗濯ロープみたいな紐を引っ張って合図し、降りる。仕事の後は、こうしてサンパウロの心臓部、パウリスタ大通りに向かった。
パウリスタ大通りからの帰宅はまずメトロ。トリアノンMASP駅からパライソ駅へ(グリーンライン)。そこで乗り換えてセー駅へ(ブルーライン)。また乗り換えて、終点のバハフンダ駅へ(レッドライン)。そこから、今度はCPTM(Companha Paulista de Trens Metropolitanos)に乗り換えてコマンダント・サンパイオ駅へ(8号線/ダイアモンドライン)。当時、バハフンダ駅には、なかなか電車がやって来ず、ホームに人が密集する頃になると、ようやく1本送られて来た。
やって来るのは、廃車にしてもよさそうなぼろぼろの電車で、ホームで待つ人が全部はいると満員になり、床に人が座り始めた。そして、この人ごみの中に、物売りたちが、かわるがわる乗り込んで来る。大きな袋に発泡スチロールでできたクーラーボックスを隠し、アイスキャンデーやビールを売る男。リュックサックからおもむろにスナック菓子を取り出して売る少年。ボールペンやアドレス帳を売る男。ヘアバンドを売る女。「1ヘアル、1ヘアル!」のかけ声が高らかに車内に響き渡る。冷たい飲み物はよく売れる。
コマンダント・サンパイオ駅からは、今度は上り坂。家に近づくほどに、舗道の段差が高くなり、自宅にも、すっかり力を使い果たして到着。
おかげで、研修中はよく眠れ、体力もついた。
ARCHIV
コマンダント・サンパイオ駅の近くに住んでいた頃、ワイン専門誌、ヴィーニョマガジン編集部でしばらく研修させてもらった。主に、編集のパウラと一緒に雑誌用のテイスティングの準備を担当した。サンパウロで働く人の目線でサンパウロを知ることができた、とても素敵な期間だった。
サンパウロ初心者にとって、一番の難関が通勤だった。サンパウロを走るバスには時刻表がない。また、バス停がわかりにくく、中には、ペイントした木材がぽつんと1本立っているだけの見落としてしまいそうな停留所もある。おまけに走行ルートがさっぱりわからない。当時は、私のポルトガル語など役立たず。掲示されている目的地とボディに取り付けられたいくつかの停留所名のリストを頼りに、思い切って乗ってしまうしかなかった。
毎朝、コマンダント・サンパイオ駅の向かいの大通りのカフェの前で、いつ来るとも知れぬ、ピニェイロス方面行きのバスを待った。ある日の待ち時間は5分ほど。ある日は30分待っても目当てのバスが来ないこともあった。バスはだいたいいつも混んでいた。運転席の方から乗って、中ほどに座っている車掌に料金を払い、回転ドアを解除してもらって奥へ。
よく揺れるのはバスがおんぼろなのか、運転が荒っぽいのか、道路が悪いのか、あるいはサンパウロの起伏のせいなのか。とにかく、どこかにしっかりしがみついていないと、カーブで飛ばされそうになる。カムフラージュのために買物用のずた袋に新聞と一緒につっこんだノートパソコンを片腕でしっかり抱いて、手すりにしがみつくこと約30分。バスを降りるといつもクタクタ。運良く座れたとしても、揺れがひどくて新聞も本も絶対に読めない。
着いたバス停から編集部までの急坂が、これまた休み休みでないと登れなかった。バスから降りると、まず停留所の近くのカフェで一休みしてから坂をのぼったことも何度か。編集部には、すっかり体力を使い果たして到着。
当然のことながら、編集長をはじめ、スタッフのほぼ全員が車で通勤していた。職場が地下鉄駅の近くにないのは致命的だ。雑誌の編集部は出勤時間にさほど制約がないからいいが、勤務時間の決まった会社に勤めている人たちは、いったいどうやって出勤しているのだろう。
ある日、私がバスと徒歩で通っていることを知った編集長が、放っておけないと言って、車で迎えにきてくれることになった。彼は、私がてっきり誰かに車で送り迎えしてもらっているものだと思っていたのだ。見習いが編集長に迎えに来てもらって悠々と出勤するなんて、なんだか立場が逆である。だから、編集長が不在で、自力通勤する日は、逆になんだかほっとした。
帰宅は、行きと違ってちょっと楽だった。急な坂を下り、いつ来るとも知れぬバスを、焦らず待つだけ。でも、仕事の帰りに中心街に寄ってから帰宅する日は勝手が違った。編集部の近くには、棒が1本あるだけのバス停があり、そこに、ジャルジン地区へ向かうバスが時々やってきた。ジェットコースターさながら急坂を猛スピードで下り、チエテ川の橋を越えると今度は渋滞がはじまる。この辺かなと思ったら、天井に張ってある洗濯ロープみたいな紐を引っ張って合図し、降りる。仕事の後は、こうしてサンパウロの心臓部、パウリスタ大通りに向かった。
パウリスタ大通りからの帰宅はまずメトロ。トリアノンMASP駅からパライソ駅へ(グリーンライン)。そこで乗り換えてセー駅へ(ブルーライン)。また乗り換えて、終点のバハフンダ駅へ(レッドライン)。そこから、今度はCPTM(Companha Paulista de Trens Metropolitanos)に乗り換えてコマンダント・サンパイオ駅へ(8号線/ダイアモンドライン)。当時、バハフンダ駅には、なかなか電車がやって来ず、ホームに人が密集する頃になると、ようやく1本送られて来た。
やって来るのは、廃車にしてもよさそうなぼろぼろの電車で、ホームで待つ人が全部はいると満員になり、床に人が座り始めた。そして、この人ごみの中に、物売りたちが、かわるがわる乗り込んで来る。大きな袋に発泡スチロールでできたクーラーボックスを隠し、アイスキャンデーやビールを売る男。リュックサックからおもむろにスナック菓子を取り出して売る少年。ボールペンやアドレス帳を売る男。ヘアバンドを売る女。「1ヘアル、1ヘアル!」のかけ声が高らかに車内に響き渡る。冷たい飲み物はよく売れる。
コマンダント・サンパイオ駅からは、今度は上り坂。家に近づくほどに、舗道の段差が高くなり、自宅にも、すっかり力を使い果たして到着。
おかげで、研修中はよく眠れ、体力もついた。
ARCHIV