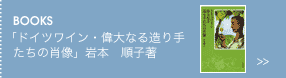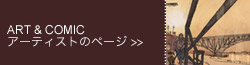TRANS・BRASIL ブラジル往復

まもなくリオの心臓部に到着

コルコヴァードの丘からパオン・ジ・アスカーを見下ろし

ロドリゴ・デ・フレイタス湖とイパネマ海岸をのぞむ

ドイス・イルマオンスをのぞむイパネマのビーチ
011「リオ 架空の街から現実の街へ」
リオ、リオ・デ・ジャネイロはずいぶん長い間、私にとって憧れの対象としてしか存在しない、ほとんど架空の街だった。友人から送られてきた絵はがきや、見せてもらった旅の写真、映画や広告などに現れる映像・・・。そういった断片的なイメージを、何度か頭の中で組み合わせようしたが、どうもうまく繋がらない。世界的に知られる大都市なのに、その地理、地形がよく理解できない。リオは、長年、そのような幻の街であり続けた。
リオという街の像がうまく結べなかった、その理由のひとつはドラマティックな地形のせいだ。例えば、生まれ故郷の神戸(リオと姉妹都市!)なら、その地形はわりと単純。六甲山系から瀬戸内海の港へ、土地は滑らかなスロープを描き、やがて海へたどり着く。東西南北は平坦な街よりもずっと解りやすい。山のない平坦なハンブルクも東から西へと、エルベ川が貫通しているため、方角はわかりやすい。
昨年2月、10回目のブラジル訪問で、ようやくリオ行きが実現した。サンパウロから飛行機に乗れば、あっという間に到着してしまう。中心街近くにあるサントス・デュモン空港への着陸時は、窓の外のめくるめく光景に興奮した。
リオの街はグアナバラ湾を形成する西側の半島の先を占めており、ほぼ三方が海に囲まれている。巨大な岩山であるモホ(Morro)が、あちこちに屹立しており、半島の先にまた半島がある。人の手による建築物よりも、自然の雄大さばかりが目にとまる。街を移動していると、次々に巨大な丘が現れ、ビルの谷間や街角に入り込むと、それがすとんと消え、やがてまた、思いがけいない形で顔をのぞかせる。宿をとったイパネマ地区からは、ビーチ側に出ると、ドイス・イルマオンス(Dois Irmãos/二人兄弟)という名の対になった巨大な丘が迫り、ラゴア(湖)側へ出るとコルコヴァード(Corcovado/瘤のある、の意)の丘をはじめ、いくつもの名も知らぬモホが現れた。
トム・ジョビン(Antonio Carlos Jobim)の有名な「Corcovado」や、カズーザ(Cazuza)の美しい曲「Um trem para as estrelas(星への列車)」に歌われた、コルコヴァードの丘と、その上に立つ救世主キリスト像(Cristo Redentor)。この標高約700メートルの丘の南側は、下から見上げても、足がすくんでしまうほどの絶壁。キリスト像は、お天気によっては雲や霧の中にすっぽりと覆われてしまい、毎日見えるわけではない。
快晴だった翌日、電力列車でこの丘に登り、初めてほんの少しだけ、リオを理解できたような気がした。コルコヴァードの丘の上で、これまで断片的だったリオのイメージがすこしだけ繋がったのだ。でもこの丘からは、どのモホも縮小され、その迫力は和らいでしまう。目の前の、あの巨大なパオン・ジ・アスカー(Pão de Açúcar)でさえ、その名の意味する円錐形の棒砂糖(ドイツ語でZuckerhut)のように手のひらにのってしまいそうだ。
サンパウロに戻る前日の夕刻、イパネマ海岸から見た夕焼けには圧倒された。それまで、遠くにしか見えなかったドイス・イルマオンスが、真っ赤な夕焼けを背に、昼間の何倍もの大きさで目の前に迫って来たからだ。あたりを見回すと、誰もが携帯電話を岩山に向け、この瞬間をカメラにおさめようとしていた。慌てて私も、赤く燃える空を背にした兄弟にカメラに向けてみたが、ディスプレイ画像には肉眼への迫力のかけらもなく、撮影は諦めて、岩山を見つめていた。リオの数々のモホは、百景どころか、無限の美景をもっている。
ドイツに戻ってから、シュテファン・ツヴァイク(Stefan Zweig/ウイーン生まれのユダヤ系ドイツ人作家。ブラジル亡命中に自ら命を絶った。)の著書「未来の国ブラジル」を手に入れた。彼はこの本の大部分をリオの描写に費やしているが、その風景描写には、読み進むほどに共感する。「・・・リオに精通することは、誰にもできない。まず第一に、海が独特のジグザグ形に海岸線を引いている。山はこれから発展すべき区域を急な斜面で邪魔している。到る所で曲がり角やカーブに突き当たる。道路は不規則な形で交差しているので、絶えず道に迷ってしまう。終点に来たと思っていると新たな始点にぶつかる・・・・」。(宮岡成次訳。河出書房新社)彼が書き留めた、今から70年前のリオの姿だ。
都会にいるのに、目にとまるのは自然ばかり。人間が造り上げたリオには、まだ一歩も足を踏み入れていないような気がする。リオはまだまだ、私にとって幻想の街であり続ける。
ARCHIV
リオ、リオ・デ・ジャネイロはずいぶん長い間、私にとって憧れの対象としてしか存在しない、ほとんど架空の街だった。友人から送られてきた絵はがきや、見せてもらった旅の写真、映画や広告などに現れる映像・・・。そういった断片的なイメージを、何度か頭の中で組み合わせようしたが、どうもうまく繋がらない。世界的に知られる大都市なのに、その地理、地形がよく理解できない。リオは、長年、そのような幻の街であり続けた。
リオという街の像がうまく結べなかった、その理由のひとつはドラマティックな地形のせいだ。例えば、生まれ故郷の神戸(リオと姉妹都市!)なら、その地形はわりと単純。六甲山系から瀬戸内海の港へ、土地は滑らかなスロープを描き、やがて海へたどり着く。東西南北は平坦な街よりもずっと解りやすい。山のない平坦なハンブルクも東から西へと、エルベ川が貫通しているため、方角はわかりやすい。
昨年2月、10回目のブラジル訪問で、ようやくリオ行きが実現した。サンパウロから飛行機に乗れば、あっという間に到着してしまう。中心街近くにあるサントス・デュモン空港への着陸時は、窓の外のめくるめく光景に興奮した。
リオの街はグアナバラ湾を形成する西側の半島の先を占めており、ほぼ三方が海に囲まれている。巨大な岩山であるモホ(Morro)が、あちこちに屹立しており、半島の先にまた半島がある。人の手による建築物よりも、自然の雄大さばかりが目にとまる。街を移動していると、次々に巨大な丘が現れ、ビルの谷間や街角に入り込むと、それがすとんと消え、やがてまた、思いがけいない形で顔をのぞかせる。宿をとったイパネマ地区からは、ビーチ側に出ると、ドイス・イルマオンス(Dois Irmãos/二人兄弟)という名の対になった巨大な丘が迫り、ラゴア(湖)側へ出るとコルコヴァード(Corcovado/瘤のある、の意)の丘をはじめ、いくつもの名も知らぬモホが現れた。
トム・ジョビン(Antonio Carlos Jobim)の有名な「Corcovado」や、カズーザ(Cazuza)の美しい曲「Um trem para as estrelas(星への列車)」に歌われた、コルコヴァードの丘と、その上に立つ救世主キリスト像(Cristo Redentor)。この標高約700メートルの丘の南側は、下から見上げても、足がすくんでしまうほどの絶壁。キリスト像は、お天気によっては雲や霧の中にすっぽりと覆われてしまい、毎日見えるわけではない。
快晴だった翌日、電力列車でこの丘に登り、初めてほんの少しだけ、リオを理解できたような気がした。コルコヴァードの丘の上で、これまで断片的だったリオのイメージがすこしだけ繋がったのだ。でもこの丘からは、どのモホも縮小され、その迫力は和らいでしまう。目の前の、あの巨大なパオン・ジ・アスカー(Pão de Açúcar)でさえ、その名の意味する円錐形の棒砂糖(ドイツ語でZuckerhut)のように手のひらにのってしまいそうだ。
サンパウロに戻る前日の夕刻、イパネマ海岸から見た夕焼けには圧倒された。それまで、遠くにしか見えなかったドイス・イルマオンスが、真っ赤な夕焼けを背に、昼間の何倍もの大きさで目の前に迫って来たからだ。あたりを見回すと、誰もが携帯電話を岩山に向け、この瞬間をカメラにおさめようとしていた。慌てて私も、赤く燃える空を背にした兄弟にカメラに向けてみたが、ディスプレイ画像には肉眼への迫力のかけらもなく、撮影は諦めて、岩山を見つめていた。リオの数々のモホは、百景どころか、無限の美景をもっている。
ドイツに戻ってから、シュテファン・ツヴァイク(Stefan Zweig/ウイーン生まれのユダヤ系ドイツ人作家。ブラジル亡命中に自ら命を絶った。)の著書「未来の国ブラジル」を手に入れた。彼はこの本の大部分をリオの描写に費やしているが、その風景描写には、読み進むほどに共感する。「・・・リオに精通することは、誰にもできない。まず第一に、海が独特のジグザグ形に海岸線を引いている。山はこれから発展すべき区域を急な斜面で邪魔している。到る所で曲がり角やカーブに突き当たる。道路は不規則な形で交差しているので、絶えず道に迷ってしまう。終点に来たと思っていると新たな始点にぶつかる・・・・」。(宮岡成次訳。河出書房新社)彼が書き留めた、今から70年前のリオの姿だ。
都会にいるのに、目にとまるのは自然ばかり。人間が造り上げたリオには、まだ一歩も足を踏み入れていないような気がする。リオはまだまだ、私にとって幻想の街であり続ける。