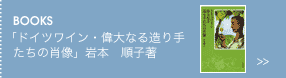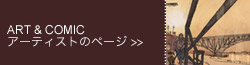WINE・WANDERING ワイン彷徨通信

Rosell Boherのエントランス

ジジ。サッカーコート3つぶんの庭にて

Rosell Boherのスパークリングワインは優しい味

ジジ&ヴァージニア夫妻と
001「雪山を臨む灼熱のメンドーサ」
今年の2月、駆け足でメンドーサを旅した。こんなにも簡単に行けるとは思わなかったので、その偶然の展開には驚くばかりだった。
ブラジルが、日本、ドイツに次いで第3番目の故郷となって、もう4年がたつ。そして、いつからか、ブラジルへ行く時には、きっちりと旅程を組まないようになった。そして、最近になってようやく、その「旅程を組まない」ことで起こるサプライズを楽しめるようになってきた。そう、ブラジルにいると、ブラジル的人助けの精神にあちこちで出会って、どんどん旅の予定変更が起こってしまうのだ。
今回も、サンパウロ往復のチケットを購入しただけで、あとは何も準備しなかった。ただ、行きたい場所だけは、しっかりとイメージしておく。できれば「どうか行けますように」とちょっぴり念じておくのだ。
「メンドーサへ行けますように」。そう思ってサンパウロに到着した。到着翌日、去年から仕事を手伝っているサンパウロのワイン専門誌「Vinho Magazine」編集部へ。すると、メンドーサ産の商品の輸出プロモーションを行う財団、プロ・メンドーサのペドロが、ガイドブック出版の打ち合わせで事務所に来ていた。社長が早速彼を紹介してくれ、しばし雑談。「え、メンドーサに行きたい? じゃあ、僕にまかせて」
ペドロは私たち夫婦の日程と予算を聞くと、旅行代理店役をかってでてくれ、数日後に安いチケットとホテルを手配してくれた。また、メンドーサ本社のニコラスに連絡をとり、現地のドライバー兼ガイドもアレンジしてくれた上、訪問したいと希望を出しておいたワイナリーのアポイントまでとってくれたのである。
あっけなくメンドーサ行きが決まってしまい、戸惑ったのはこちらのほうだ。「あっ、早速ジジに連絡しなくちゃ!」
ジジ。本名はルイス・マーティネス。2004年にワインの審査の仕事で知り合い、以来毎年1度ドイツで顔を合わせるメンドーサのエノロジスト。会うたびに、いつくるんだと言われ、いつかきっと、と言いつつ、4年の歳月がたっていた。日程が決まると早速ジジにメールを書いた。でも、全然返事がこない。彼の自宅に電話もかけてみたが、誰もでない。
そうこうするうちに出発日となり、ジジとは全然連絡がとれないまま、ブエノス・アイレスの国際空港に到着。バスで国内線の空港へ移動し、そこから1時間ほどでメンドーサに到着した。ブエノス・アイレスでは滝のような雨に襲われたが、メンドーサでは強烈な日光と砂埃に包まれた。ホテルからまたジジに電話する。誰も出ない。メールを送る。返事はない。
2泊3日の滞在中、一体何度、電話をかけただろうか。それにしても、私ものんきなもので、彼が勤務する国立ぶどう栽培・ワイン醸造研究所の電話番号を調べ、連絡するということを最後まで思いつかなかった。今日はもう帰るという日の朝、慌てて彼の仕事場の電話番号をインターネットで調べ、電話をしてみた。何度もたらい回しになったが、ジジが出た。「フンコ!」ジジは私の名前をスペイン式にこう呼ぶ。
私たちは、この日3つのワイナリーのアポイントをとっていたが、最後のワイナリー訪問をキャンセルし、ジジの自宅へ向かった。出発までの約2時間を、彼と過ごした。
私はこの日まで何も知らなかったのだが、ジジの実家は1900年創業の伝統あるワイナリー「Rosell Boher(ロセル・ボエール)」なのだった。醸造所は長年荒れるがままになっていたが、1999年に、ジジの弟、アレハンドロ・マーティネス=ロセルが中心となって再建、以後、主に高品質のシャンパーニュ製法によるスパークリングワインを生産している。
ジジの家は、醸造所の真横にあった。灼熱の太陽が降り注ぐこの日、サッカーコート3つぶんもある一家の広大な庭から真っ白な雪山がくっきりと見えた。その後、彼の案内で、醸造所を見学し、スパークリングワインを中心にテイスティング。シャンパーニュ地方エペルネの「Deutz(ドゥーツ)」と情報交換しあっているという、スパークリングワインの美味しさもさることながら、私はこの日、限りなくエレガントな香りと味のソーヴィニヨン・ブランを味わった。旅の興奮、出会いの興奮のまっただ中にいたせいもあるだろうけれど、ソーヴィニヨン・ブランを飲んで、これほど感動したのは初めてのこと。ロセル・ボエールの2007年のソーヴィニヨン・ブランの衝撃は、今から約10年前の、ケラー醸造所のリースリングの衝撃に通じるものがあった。
「ソーヴィニヨン・ブランはメンドーサで大きな可能性を秘めた品種」メンドーサのワインを、長年分析し、評価してきた彼はそう言う。このソーヴィニヨン・ブランと未来のソーヴィニヨン・ブランを味わうために、メンドーサのワインの発展を、全て舌で味わってきたジジの話をもっと聞くために、またメンドーサに来よう、そう強く思った。
ARCHIV
今年の2月、駆け足でメンドーサを旅した。こんなにも簡単に行けるとは思わなかったので、その偶然の展開には驚くばかりだった。
ブラジルが、日本、ドイツに次いで第3番目の故郷となって、もう4年がたつ。そして、いつからか、ブラジルへ行く時には、きっちりと旅程を組まないようになった。そして、最近になってようやく、その「旅程を組まない」ことで起こるサプライズを楽しめるようになってきた。そう、ブラジルにいると、ブラジル的人助けの精神にあちこちで出会って、どんどん旅の予定変更が起こってしまうのだ。
今回も、サンパウロ往復のチケットを購入しただけで、あとは何も準備しなかった。ただ、行きたい場所だけは、しっかりとイメージしておく。できれば「どうか行けますように」とちょっぴり念じておくのだ。
「メンドーサへ行けますように」。そう思ってサンパウロに到着した。到着翌日、去年から仕事を手伝っているサンパウロのワイン専門誌「Vinho Magazine」編集部へ。すると、メンドーサ産の商品の輸出プロモーションを行う財団、プロ・メンドーサのペドロが、ガイドブック出版の打ち合わせで事務所に来ていた。社長が早速彼を紹介してくれ、しばし雑談。「え、メンドーサに行きたい? じゃあ、僕にまかせて」
ペドロは私たち夫婦の日程と予算を聞くと、旅行代理店役をかってでてくれ、数日後に安いチケットとホテルを手配してくれた。また、メンドーサ本社のニコラスに連絡をとり、現地のドライバー兼ガイドもアレンジしてくれた上、訪問したいと希望を出しておいたワイナリーのアポイントまでとってくれたのである。
あっけなくメンドーサ行きが決まってしまい、戸惑ったのはこちらのほうだ。「あっ、早速ジジに連絡しなくちゃ!」
ジジ。本名はルイス・マーティネス。2004年にワインの審査の仕事で知り合い、以来毎年1度ドイツで顔を合わせるメンドーサのエノロジスト。会うたびに、いつくるんだと言われ、いつかきっと、と言いつつ、4年の歳月がたっていた。日程が決まると早速ジジにメールを書いた。でも、全然返事がこない。彼の自宅に電話もかけてみたが、誰もでない。
そうこうするうちに出発日となり、ジジとは全然連絡がとれないまま、ブエノス・アイレスの国際空港に到着。バスで国内線の空港へ移動し、そこから1時間ほどでメンドーサに到着した。ブエノス・アイレスでは滝のような雨に襲われたが、メンドーサでは強烈な日光と砂埃に包まれた。ホテルからまたジジに電話する。誰も出ない。メールを送る。返事はない。
2泊3日の滞在中、一体何度、電話をかけただろうか。それにしても、私ものんきなもので、彼が勤務する国立ぶどう栽培・ワイン醸造研究所の電話番号を調べ、連絡するということを最後まで思いつかなかった。今日はもう帰るという日の朝、慌てて彼の仕事場の電話番号をインターネットで調べ、電話をしてみた。何度もたらい回しになったが、ジジが出た。「フンコ!」ジジは私の名前をスペイン式にこう呼ぶ。
私たちは、この日3つのワイナリーのアポイントをとっていたが、最後のワイナリー訪問をキャンセルし、ジジの自宅へ向かった。出発までの約2時間を、彼と過ごした。
私はこの日まで何も知らなかったのだが、ジジの実家は1900年創業の伝統あるワイナリー「Rosell Boher(ロセル・ボエール)」なのだった。醸造所は長年荒れるがままになっていたが、1999年に、ジジの弟、アレハンドロ・マーティネス=ロセルが中心となって再建、以後、主に高品質のシャンパーニュ製法によるスパークリングワインを生産している。
ジジの家は、醸造所の真横にあった。灼熱の太陽が降り注ぐこの日、サッカーコート3つぶんもある一家の広大な庭から真っ白な雪山がくっきりと見えた。その後、彼の案内で、醸造所を見学し、スパークリングワインを中心にテイスティング。シャンパーニュ地方エペルネの「Deutz(ドゥーツ)」と情報交換しあっているという、スパークリングワインの美味しさもさることながら、私はこの日、限りなくエレガントな香りと味のソーヴィニヨン・ブランを味わった。旅の興奮、出会いの興奮のまっただ中にいたせいもあるだろうけれど、ソーヴィニヨン・ブランを飲んで、これほど感動したのは初めてのこと。ロセル・ボエールの2007年のソーヴィニヨン・ブランの衝撃は、今から約10年前の、ケラー醸造所のリースリングの衝撃に通じるものがあった。
「ソーヴィニヨン・ブランはメンドーサで大きな可能性を秘めた品種」メンドーサのワインを、長年分析し、評価してきた彼はそう言う。このソーヴィニヨン・ブランと未来のソーヴィニヨン・ブランを味わうために、メンドーサのワインの発展を、全て舌で味わってきたジジの話をもっと聞くために、またメンドーサに来よう、そう強く思った。