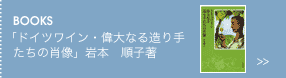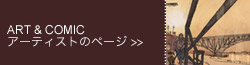WINE・WANDERING ワイン彷徨通信

こんな風景のところどころにぶどう畑が

パスタ作りの名人。袋の中はカペレッティ

アンジェラの家の食卓

アンジェラのおばあちゃんのポレンタ
003「イタリアンフードの里」
初めて、ブラジルのワイン産地を旅したとき、そこがもうひとつのイタリアのような場所だとは、想像だにしなかった。サンパウロの中心に、小さな日本のような街区があることが想像できなかったのと同じだ。
80年代から90年代にかけて、イタリア語もわからないのに、北から南へと、イタリアばかり旅していた時期があった。あれから何年もたった今、ブラジルの南端で、こんなかたちでイタリアと再会しようとは!
ブラジル最南端、リオ・グランジ・ド・スル州の最初の住民は、インディオやガウーショ(牧畜業を営むスペイン系の人々)たちだった。その後、ポルトガル系、アフリカ系、ドイツ系、イタリア系、ポーランド系など、あらゆる国の人たちが集まってきた。
ベント・ゴンサウヴェス市を中心とするワイン地方一帯の住民は、ほとんどがイタリア系、ワインの造り手となると、ほぼ100%イタリア人の子孫。1世たちの多くは、イタリア北部、主にヴェネト地方の、貧しい農民だった。1875年から1914年にかけて、約10万人のイタリア人が、豊かさを求めてこの地へやってきた。
この地方で、ごく普通のレストランに入り、定食を注文すると、まずカペレッティが出て来る。ブロードの中に、カペレッティと呼ばれる詰め物入りの小さなパスタが浮かんだスープだ。メインの肉料理は、ブラジリアンスタイル(ガウーショスタイル)の炭火焼きの牛肉や鶏肉が主だが、それには必ずポレンタが添えられる。ブラジル風にアレンジされたピッツアも美味しく、カリっと香ばしい縁の中にまでチーズが詰まっていることもある。
いつだったか、カサ・ヴァルドゥーガ醸造所直営のレストランのスタッフが、こんなことを言っていた。「イタリアからやってくる観光客の多くが、ここで僕たちのイタリア料理を味わい、その素朴な美味しさに感激して帰ってゆくんだよ」と。そういえば私も、サンパウロの日本料理屋で、素朴で懐かしい、田舎のおばあちゃんの味つけみたいな和食に出会って感激することがある。イタリア人も、ブラジルで似たような体験をしているなんて!
ある日、友人のダグラスにフローレス・ダ・クンニャ(Flores da Cunha)近郊、オタヴィオ・ホシャ(Otávio Rocha)にある手打ちパスタの工房(カサ・デ・マッサス/Casa de Massas)に連れて行ってもらった。イタリア系のご主人が、ちょうど古いパスタマシンでスパゲティをつくっておられた。そこへ、近所の人たちが、焼きたてのパンでも買うかのように、フレッシュな麺を買いにくる。なんだか、イタリアの田舎にでも迷い込んだみたいな光景だった。
出発の前夜は、ラボでワインの分析の仕事をしている友人、アンジェラのカシアス・ド・スル(Caxias do Sul)にある実家で、おばあちゃんの手料理をご馳走になった。彼女の家族も、やはりイタリア系だ。大鍋一杯のポレンタ、チキンの煮込み、新鮮なトマトと苦みのあるハディッチ(Radicci)のサラダ。食事だけではない。ダイニングキッチンの色彩や空気までもが、20年以上前に訪れた、ミラノの郊外に住む友人宅の食事時を思い起こさせた。
地元では、ピエモンテ地方のアスティ・スプマンテを再現したスパークリングワインがよく売れていた。モスカート種でつくられた上品な甘さのスパークリングワインは、アペリティフやデザートワインとして、とても愛されているようだった。料理に供するワインは、カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランなどフランス品種のものがほとんどだが、ブラジルの太陽の下、ぶどうが充分に熟すため、青草の香りが全く感じられない。最近では、イタリア系品種のネッビオーロやサンジョヴェーゼも栽培されはじめているという。造り手たちのイタリアの遺伝子は、フランス品種での経験を積んだいま、イタリア品種のワインを求めはじめているのだろう。
ARCHIV
初めて、ブラジルのワイン産地を旅したとき、そこがもうひとつのイタリアのような場所だとは、想像だにしなかった。サンパウロの中心に、小さな日本のような街区があることが想像できなかったのと同じだ。
80年代から90年代にかけて、イタリア語もわからないのに、北から南へと、イタリアばかり旅していた時期があった。あれから何年もたった今、ブラジルの南端で、こんなかたちでイタリアと再会しようとは!
ブラジル最南端、リオ・グランジ・ド・スル州の最初の住民は、インディオやガウーショ(牧畜業を営むスペイン系の人々)たちだった。その後、ポルトガル系、アフリカ系、ドイツ系、イタリア系、ポーランド系など、あらゆる国の人たちが集まってきた。
ベント・ゴンサウヴェス市を中心とするワイン地方一帯の住民は、ほとんどがイタリア系、ワインの造り手となると、ほぼ100%イタリア人の子孫。1世たちの多くは、イタリア北部、主にヴェネト地方の、貧しい農民だった。1875年から1914年にかけて、約10万人のイタリア人が、豊かさを求めてこの地へやってきた。
この地方で、ごく普通のレストランに入り、定食を注文すると、まずカペレッティが出て来る。ブロードの中に、カペレッティと呼ばれる詰め物入りの小さなパスタが浮かんだスープだ。メインの肉料理は、ブラジリアンスタイル(ガウーショスタイル)の炭火焼きの牛肉や鶏肉が主だが、それには必ずポレンタが添えられる。ブラジル風にアレンジされたピッツアも美味しく、カリっと香ばしい縁の中にまでチーズが詰まっていることもある。
いつだったか、カサ・ヴァルドゥーガ醸造所直営のレストランのスタッフが、こんなことを言っていた。「イタリアからやってくる観光客の多くが、ここで僕たちのイタリア料理を味わい、その素朴な美味しさに感激して帰ってゆくんだよ」と。そういえば私も、サンパウロの日本料理屋で、素朴で懐かしい、田舎のおばあちゃんの味つけみたいな和食に出会って感激することがある。イタリア人も、ブラジルで似たような体験をしているなんて!
ある日、友人のダグラスにフローレス・ダ・クンニャ(Flores da Cunha)近郊、オタヴィオ・ホシャ(Otávio Rocha)にある手打ちパスタの工房(カサ・デ・マッサス/Casa de Massas)に連れて行ってもらった。イタリア系のご主人が、ちょうど古いパスタマシンでスパゲティをつくっておられた。そこへ、近所の人たちが、焼きたてのパンでも買うかのように、フレッシュな麺を買いにくる。なんだか、イタリアの田舎にでも迷い込んだみたいな光景だった。
出発の前夜は、ラボでワインの分析の仕事をしている友人、アンジェラのカシアス・ド・スル(Caxias do Sul)にある実家で、おばあちゃんの手料理をご馳走になった。彼女の家族も、やはりイタリア系だ。大鍋一杯のポレンタ、チキンの煮込み、新鮮なトマトと苦みのあるハディッチ(Radicci)のサラダ。食事だけではない。ダイニングキッチンの色彩や空気までもが、20年以上前に訪れた、ミラノの郊外に住む友人宅の食事時を思い起こさせた。
地元では、ピエモンテ地方のアスティ・スプマンテを再現したスパークリングワインがよく売れていた。モスカート種でつくられた上品な甘さのスパークリングワインは、アペリティフやデザートワインとして、とても愛されているようだった。料理に供するワインは、カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランなどフランス品種のものがほとんどだが、ブラジルの太陽の下、ぶどうが充分に熟すため、青草の香りが全く感じられない。最近では、イタリア系品種のネッビオーロやサンジョヴェーゼも栽培されはじめているという。造り手たちのイタリアの遺伝子は、フランス品種での経験を積んだいま、イタリア品種のワインを求めはじめているのだろう。